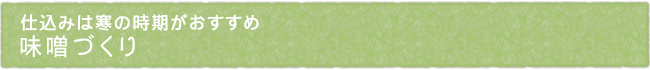2011/01/05 作成
やってみると意外なほど簡単で、初心者でも失敗が少ない味噌づくり。雑菌の繁殖が少ない1~3月の寒い季節は味噌の仕込みに最適です。材料は、大豆・こうじ・塩のみといたってシンプル。国産有機大豆や国産有機こうじ、自然塩など、自分で納得のいく材料が選べるのも手づくり味噌の良いところです
手づくり味噌は、仕込んでから6ヶ月を過ぎた頃から食べ始められます。熟成による味や香り、色などの変化を楽しみながら、自分で好みの味を見極めるのがおすすめです
仕込んだ味噌は、6ヶ月を過ぎたころから食べることができ、1年ほど熟成すると味に深みが出てきます。玄米こうじを使った味噌は熟成期間が長く、1年半~2年が目安です。好みの味に熟成したところで密封容器に入れ、冷蔵庫で保存することで熟成速度を抑えることができます




<材料>
大豆…1kg
こうじ(米・玄米・麦共通)…1kg
塩…450g
種汁(大豆の煮汁)…200cc
<作り方>
- 一晩(8~10時間)水にひたした大豆を鍋に入れ、たっぷりの水でアクを取りながら4~5時間煮る
※むけた大豆の皮は吹きこぼれの原因になるので取り除いておく。指でカンタンに潰せるくらいまで煮るのが目安 - こうじと塩をかたまりがなくなるようにまんべんなく混ぜる。出来上がったものを「塩切りこうじ」と呼ぶ
- 煮大豆が冷めないうちに、塩切りこうじを均一になるように混ぜ合わせる
※大豆の煮汁は、材料にある「種汁」になるので、捨てずに取っておく - 材料をつぶす。すり鉢やフードプロセッサーなどを使うと便利。よくつぶせば、口当たりのなめらかな味噌に、粗めにつぶせば、大豆の粒の残ったワイルドな味噌に仕上がる
- つぶした大豆に種汁を加えて、ハンバーグの種程度の固さにする。それをお団子状にしてカメ(保存容器)にたたきつける
- 最後に表面を平らにならし、焼酎を吹きかけラップを貼り付ける。落とし蓋をのせ、ほこりが入らないように布や紙をかぶせる
※落とし蓋がない場合は、漬物石などを代用してもよい - 風通しがよく、直射日光が当たらない場所で保存し、つゆ明けに切り返し作業をする
※切り返し作業=表面のカビをとり、カメ(保存容器)の中の味噌をかき混ぜること。この後は、重石の必要はありません
国産農産物と調味料を使って、世界に一つの我が家の味を作りましょう。玄米こうじを使うと、よりコクがある味噌ができ、麦こうじを使うと、香りの良い、ほんのり甘めの味噌に仕上がります。また、こうじの割合を多くすると味噌に甘みが出ます

【有機大豆】300g/1kg
中里町自然農法研究会(青森)/ポラン オーガニックフーズ デリバリ(東京)
甘み・旨みが強く、風味豊かな大豆です。味噌づくりはもちろん、煮豆にするとふっくらやわらかく煮あがります
生産者・中里町自然農法研究会代表の三上新一さんは、1962年の就農以来、有機農業に取り組んでいます。1994年には「中里町自然農法研究会」を組織し、代表として農業指導をはじめ、地域の活性化に尽力しています

【有機米こうじ】1kg
【有機玄米こうじ】1kg
【やさか麦こうじ】1kg
やさか共同農場(島根)
こうじとは蒸した穀物にこうじ菌と呼ばれる微生物を繁殖させたもの。こうじ菌は室町時代から続く京都「菱六」製を使用しています。【有機米こうじ】【有機玄米こうじ】は、やさか共同農場の有機米を使用。米こうじは醗酵がうまくいくので初心者向き。【やさか麦こうじ】は、広島産、農薬・化肥不使用の裸麦を使用

【海の精(赤ラベル)】170g/350g/3kg
【海の精漬物塩】1.5kg
海の精(東京)
伊豆大島の海水でつくった純国産の自然海塩。立体式塩田に汲み上げ、風と太陽熱を利用して濃縮した海水を、釜で煮詰めました。ただ塩辛いだけでなく、ほのかな甘味や苦味、酸味があります。【海の精漬物塩】は、【海の精(赤ラベル)】より精製の工程を減らした徳用品。味噌づくりや漬物づくりに最適です

【切り立ちカメ 蓋付き】2号/3号/4号/5号/8号
【落とし蓋】小/中/大/特大
ヤマタネ(愛知)
日本六古窯のひとつに数えられる「常滑焼」の陶器です。焼きがしっかりしていて、釉もなめらか。外気温の当たりが柔らかく、夏場も安心です。温度変化が少ないため、乳酸菌・酵母菌等の有用微生物を増殖させ、腐敗菌等の有害微生物の繁殖を防ぎます。【落とし蓋】も、接着剤を使っている合板ではなく、陶器の落し蓋を。重石より均等に重量がかかります